この俳優、魅力的につき 第1回 大石将弘(ままごと/ナイロン100℃/スイッチ総研副所長)【前編】
この俳優、魅力的につき
2015.09.15
「演出家の時代」と言われて久しい。それを反映するかのように、演劇人へのまとまったインタビューは、圧倒的に演出家、劇作家が多い。しかし最近、俳優発信の企画が目に付くなど、刺激的な小劇場を形成する俳優の存在感が高まっている。観る演劇は基本的に演出家で選ぶ徳永京子が、その中核にいる、気になって仕方のない彼/彼女にじっくり話を聞く。
* * *
第1回 大石将弘(ままごと/ナイロン100℃/スイッチ総研副所長)【前編】
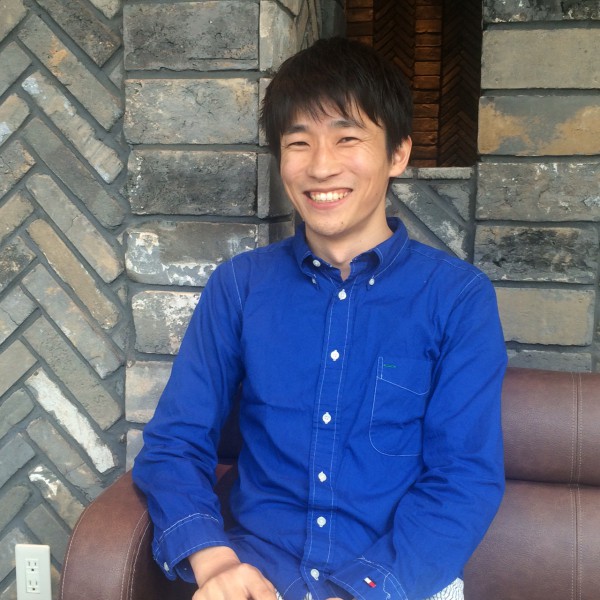
俳優としては特徴の少ないルックスで、演技の押し出しも強くない。なのに、終わってみれば深い印象を残す。西からゆっくりやって来た俳優が静かにつくった居場所は、新しい楽しみ方をする演劇の拠点となって、その活動領域を一気に広げようとしている。
* * *
おおいしまさひろ。俳優。1982年生まれ、奈良県出身。10年よりままごと、14年よりナイロン100℃に所属。15年、俳優・光瀬指絵と共に、観客が何らかのスイッチを押すと、待機していた俳優による3秒〜30秒の小さな演劇「スイッチ」を上演するスイッチ総研を立ち上げる。これまでの主な出演作品は、ままごと『スイングバイ』(10年)、太宰治の『女生徒』を下敷きにしたひとり芝居の『朝がある』(12年)、『日本の大人』(13年)、マームとジプシー『Kと真夜中のほとりで』(11年)、 NODA・MAP『エッグ』(12年)、日本劇団協議会『SEX,LOVE&DEATH』(13年)、FUKAIPRODUCE羽衣『女装、男装、冬支度』(14年)、『象の鼻スイッチ』(13年)、『六本木アートナイトスイッチ』(15年)など。
* * *
真面目な帰宅部から、落ちるための受験へ
──大石さんに興味がある人は多いと思うんですけど、これまでの経歴がわかるインタビューはあまりないですよね。なので、最初の最初からお聞きしてもいいですか?
「ええと……生まれたところから?」
──どんな子供だったか、あたりからでお願いします(笑)。
「クラスのおもしろい子を横目で見ているタイプでした。笑いを取れるヤツを妬んで、羨ましがってる、でも自分では何も出来ない。休み時間も自分の椅子から動かない子でした。話をする友達はいましたけど、そんなに多い方ではなくて、基本的に固定の数人で遊んだり喋ったり」
──運動神経がいいイメージがあるので、休み時間は校庭派なのかと思っていました。
「そういうイメージ、ありますか? 運動は中学の時にバスケをやってました。完全に漫画の『スラムダンク』の影響で始めたんですけど、3年間打ち込みました。でもうちの学校は弱くて、僕はそこでもレギュラーにもなれなかったくらいだから、全然上手くなかったです。それと、練習がかなり厳しくて、高校に入る時に、もう運動部はいいや、と思いまして。何か他のことと思ううち部活に入りそびれて、結局、帰宅部になったんです。これが間違いで、まるで定年退職したお父さんみたいになってしまって。“自由に何でもやっていいよ”という時間があると、何をしていいかわからない。結局、家で漫画読んだりテレビ見たり、友達の影響でギターをちょっとかじってみたりしたんですけど続かず……。あとはまぁ、割と勉強が出来たので勉強ばっかりしてました」
──共学ですか?
「はい。でも女の子とは全く喋れなかったです、畏れ多くて。よくみんな、高校時代が1番楽しかった、戻りたいとか言いますけど、僕は絶対に戻りたくないです」
──文化祭や体育祭は?
「逃げてました。クラスの“楽しくやろうぜ!”みたいなノリに着いていけず、似たような仲間と図書室でサボったり。自分が出る演目だけやったらすぐ帰ってました」
──それは「そんなことに夢中になるなんて、あいつらガキだな」的な?
「いやいや、そうじゃないです。だって彼らはコミュニケーション能力の高い人達ですから。僕は、他愛ない話すらできない。進学校だからみんな勉強も出来るし、部活やってる人は運動も出来る。そうやって楽しくやってる人達が羨ましかったです。見下すんじゃなくて見上げてました」
──楽しくはなかったけど学校に行って、帰って来て粛々と勉強する、判で押したような3年間。
「そうですね。やることといったら勉強と、漫画読むのとテレビ観るくらいで。家に帰ったら5時、6時で、宿題やって、ご飯食べて、テレビ見てだらだらしてたら10時、11時になって。で、お風呂入ったら1日が終わる。でも、そういうもんだと思ってましたね。自分はそういう生活を送るしかない、というか」
──将来についてもそう考えていたんですか?
「このまま大学入って、理系か何か職種はわからないですけど、定時で働いて帰るような、ルーチンワークが向いてるんだろうと思ってました。それを60歳まで続けて定年で退職するイメージを漠然と持ってたというか、自分の適正と世の中の都合を考えると、それが1番しっくり来ると思ってたんです。でも同時に、それが嫌だとも思ってて。なんかやりたいのになっていう気持ちだけがあって、高3の大学受験ギリギリの時期に葛藤があって、芸大や美大に進む選択を考えるようになりました。」
──ものすごい急展開ですね。
「もともと絵を描くのは好きだったのと、テレビドラマやアニメの影響で、書いたり作る人になることへの憧れはあったんです。それで芸大の資料を取り寄せたら、合格者のデッサンや作品が載ってて、当然ですけど、もうレベルが全然違う。これはどうしようもないなと思って、いわゆる総合大学を受験することにしました。でもその時に無理して偏差値のランクが1つ上の大学を受けたんです、落ちようと思って。落ちたら浪人して、自分の将来というか、どういう道に進むか考える猶予にしようと。そしたら受かってしまった。両親や先生も喜んじゃって、まぁ、じゃ、行こうかなって」
──どちらの大学かお聞きしていいですか?
「大阪大学です。入学して、何か作品を作ることに関わりたくて、映画のサークルを覗いたりしたんですけどちょっと雰囲気が合わなそうで。どうしようか考えていた時にたまたま学内で演劇の公演があって、それを観たのがたぶん生まれて初めての、鑑賞授業じゃない演劇だったんですけど、すごくおもしろかったんです。演劇をよく知らない人が持ってる演劇のイメージってあるじゃないですか。かっこいいせりふを正面切って言って、汗かく感じの。当時は、それだったら多分引いてたと思うんですけど、そうじゃなくて、笑いがあって、ちょっとシニカルで、でもかっこつけてない芝居だったんです。これならと思って、その劇団に入ったのが18歳です」
変わった大人達と、「役」という役割との出会い

──大学の学生劇団だったんですか?
「普通、学生劇団って言ったら、メンバーは全員学生で4年で卒業していくじゃないですか。その劇団は特殊で、学校に寄生してる、大阪の劇団だったんです。中心メンバーが大阪大学のOBというだけでずっと居残ってるという(笑)。主宰が僕の2まわり上で、当時42歳でした。その人が作・演出をして。学生を新劇団員にすると学内の設備を無償で使えるからずっとそのままという。㐧2劇場っていって今もあるんですけど。そういう劇団だから全然学生のノリじゃなくて、飲みに行くのも、大人な、と言うよりおっさんの飲み屋でした。そこがおもしろかったんですね。それまで基本的には同世代としか触れ合う機会がなかったのが、その劇団に入って、世の中には変な大人がいるんだとわかって……。みんな働きながら芝居をやってるけど、大学に居残りながらやってるくらいだから変な人達ばっかりで。その人達の話はおもしろかったですね、聞くのも話すのも」
──ずっとできなかった他愛ない会話ができるようになったのは、その人達が大人だったからですかね?
「他愛ない話はやっぱり出来なかったけど、お芝居をつくるとなると、どうしてもコミュニケーションを取らなきゃいけないじゃないですか。それぞれの役割があって、自分にも役割があてがわれて、最初はそれをどうすればいいからわからないから聞く、で、教えてもらうっていう、明確な目的があるコミュニケーションだから、出来たんだと思います。」
──演劇の楽しさもすぐに感じられたんですか?
「僕が入った年は、同期が僕ともうひとりだけだったんですよ。で、学生の先輩も3年生がひとりで、4年生がひとりかふたりだけで。若い人が少なかったこともあって、1年生の時から比較的出番が多い役で使ってもらっていました。その作・演出家の作品が好きで、やっていて楽しかったです」
──失礼ですけど、お名前は?
「四夜原茂(しやはらしげる)っていう人です。俳優を矯正して自分の作品に近づけるというより、役者には自由にやらせて、おもしろさを担保するために全体のバランスを整えていくようなやり方で。役者は、自分のままというか、無理をしないお芝居が出来る環境だったと思います。」
──ずっと持っていた「自分も何かしたい」といううっすらしたストレスに対して、㐧2劇場に入って「あ、これだ!」という手応えがあった?
「多分、あったんだと思います。そのストレスは、今考えるとうっすらじゃなくて結構明確に溜まってました。クラスでおもしろい発言をしたり、おもしろい作文を書いたり、おもしろい絵を描いたり、したいんだけど軒並み出来ないっていうことにずっと困ってた。やりたいけど出来ない人はどうしたらいいんだと。演劇を始めて、俳優が割と自分の性に合ってたなって思うのは、まず、自分で台本を書かなくていい。おもしろい台本を誰かが書いてくれれば、そのおもしろさを損なわずに、決められたせりふを言って演じることが出来れば、お客さんが笑ってくれるっていうのが素晴らしいことだと思ったんです。“自由に何でもどうぞ”は出来ないけど、制約──決められた段取りやせりふ──の中で最大限、自分のおもしろいと思うことを仕込んだり企んだりするのが、きっと、ゼロから何かをつくるよりも向いてたんだと思います。それが発見できたので」
──でも、自分は俳優に向いているようだと思える外からの反応もありましたよね?
「最初に出させてもらったやつで褒めてもらったのかな、お客さんや先輩に。それで、どうやら悪くはないらしいぞ、と。」
──大学の4年間は、俳優に打ち込むことに?
「えーと、2年生になった頃から、やっぱり自分でも何かやりたいって考えるようになっていったんですね。それで、1学年下にお笑いをやりたい子がいて、彼とコント公演をやったりもしました。ネタは彼が書いて演出もしてくれて。僕はずっとツッコミで、最初はそんなでっかい声でツッコむの恥ずかしいわって思ってたんですけど“ツッコミってお客さんに近い立場だから、変なことが起こってることに対して、お客さんが気付く半歩手前ぐらいで、ちゃんとわかりやすく指摘してあげることが大切なんだ”と。確かにそうやったら、自分が空気をつかまえる感じがちょっとあったんですよ。演劇じゃなくてコント(でそれに気付くの)かよ、って感じなんですけど(笑)、このタイミングで、このボリュームで、この音で入ればおもしろいんだってことが、ちょっとわかった気がしたんですね。台本読んでやりたいようにやるんじゃなくて、お客さんと舞台上の要請を受けて自分が何をどう出すかっていうことに、自覚的になりました。それと3年生の4月に、自分でもお芝居をつくりました。松尾スズキさんの原作をお借りして、自分で演出をして、出演者は大学内の他の劇団の人や別の大学の人に声かけて。その時に、演出は向いてないなっていうことがわかったんですけど、自分たちで公演を打つことはすごい楽しかった。楽しかったと言うか、充実感があった。俳優として出るだけでは得られない大変さとおもしろさを感じました。」
──卒業後もずっと俳優をしようと?
「1年生のGWから授業に出てなかったんです。当然、単位が足りなくて、結局、卒業に2年余分にかかったんですね。そうすると、後輩達の方が先に卒業していく。彼らは、ちゃんと4年で卒業して就職していった。大学の仲間と劇団をやるという選択を失って、自分がフリーの俳優で関西でやっていくことを、上手く思い描けなかった。バイトに追われ、ノルマを払いながら演劇をやるのはいやだなと思って、就職することにしました」
≫後編はコチラ



