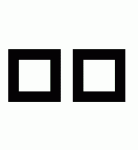ロロ『四角い2つのさみしい窓』三浦直之インタビュー
インタビュー
2020.01.24

あっちとこっちを分ける窓があるとして、
それを溶かして対立をなくした道にしたいんです。
10周年を迎えた昨年、ひとつの劇団の誕生から消滅までを、ある女性の孤独との向き合い方、ふたりの女性の出会いと別れ、歌の始まりと広がり、森の生態など、さまざまな事象と絡めた『はなればなれたち』で描いたロロ。劇団そのものもまた、全員でハーモニーを奏でるのでなく、各メンバーが異なるリズムやメロディを奏で、それがひとつのグルーヴを生み出す緩やかな連なりとなった姿を見せたように思う。結成当初は「boy meets girl」の物語を看板にしていた彼らは、meetのあとの長い時間をスタートさせた。賑やかなゲストを迎えた前作から一転、劇団員だけの10周年記念公演の第2弾『四角い2つのさみしい窓』は全国4都市ツアーを敢行中。主宰・脚本家・演出家の三浦直之に話を聞いた。
── 戯曲を読んだ印象ですが、前作『はなればなれたち』と似た感触もありつつ、それより強く思い出したのは、再演版の『父母姉僕弟君』(17年)でした。
三浦 そうですね。僕も最初は『はなればなれたち』のあとに何を書くかを考えて進めていったんでんですけど、書いていくうちに「あ、これは『父母姉僕弟君』をアップデートしていく話だな」と思いました。『父母姉僕弟君』は擬似家族がモチーフで、どうやって父から父の権力を奪うかの話だったんですけど、今回も疑似家族というところから出発しています。
── 話の立ち上げとしてはどこから?
三浦 10周年記念として自主公演で2本連続で打つのは最初から構想していました。内容は、『はなればなれたち』で“これまで”を、つまり登場人物達が子ども時代から始まって30歳ぐらいで終わる話にして、『四角い2つのさみしい窓』は自分達の同世代かちょっと上ぐらいの登場人物をイメージしたんです。次に上演した時にメンバーの年齢がハマっていくといいなと、そもそも再演を想定しながら書きました。
── 今を起点として、過去から今までが第1弾、今から未来が第2弾というセットで企画した。
三浦 はい。それと『四角い2つのさみしい窓』は出演者がメンバーだけだから、まずお客さんにメンバーを存分に楽しんでほしい気持ちがありました。そのためには(複数の役を)演じ分けるのが良いんじゃないかと。そこから2つの世界を切り替えながら書いていこうと考えたのがひとつと、もうひとつは『はなればなれたち』が別れの話だったので──僕としてはそのつもりはないんですけど、ストーリー上は別れて終わったので、結構な数のお客さんから「解散するの?」とメンバーが聞かれたらしいんです──、じゃあ再会の物語を書こうと。
── 今回、劇団員だけと言っても、メンバー全員は揃わないんですよね。
三浦 当初は6人全員でと考えていたんですが(板橋)駿谷さんが出られなくなりました。前回は亀島(一徳)くんが出られなくて、きっとたぶん、今後もメンバー全員が揃うことは少なくなっていくと思うんですよ。ただ、それでもそばにいるというか、そばにいるのとはちょっと違うかもしれないけど、いないということではない、みたいな意識はあって。“不在の在”みたいなことも込みで集団を考えています。
── 『はなればなれたち』のエンディング、私は、淋しい空気は流れていたけれども「別れると離れるは違う」と感じたんですね。それぞれの道が分かれても、どこかでまたくっつけばいいという。
三浦 この前、ふと20年後を考えた時に、メンバーはもう誰もいなくなってひとりでやっているだろうなっていうのと、まだみんなと一緒にやっているなっていうのが、同じレベルで想像できたんですよ。『はなればなれたち』の離れたまま一緒にいる感覚が、自分にとってはすごくリアリティがあるんだと思います。
── その感覚は最近獲得したものですか? というのは、振り返ってみると『ハンサムな大悟』(15年)は、ひとつの生命体の中の細胞の分裂とか、人の形がなくなって土と融合する形態が描かれていたので、三浦さんの中では以前からずっと分裂と結合、分離と融合への関心があって、それが“不在の在”のおおもとになったのかと、今、思ったのですが。
三浦 この何年かという気がします。「あのメンバー、辞めるかもな」「ロロ、解散するかもな」と本当に思った瞬間がここ2年ぐらいの間で何回かあって、それから自分の中で問題意識が大きくなっていった気がします。それと僕、誰かとしっかりお別れをするという経験をあまりしていなくて。恋人と別れるといったことも全然上手にできないから、いつか来る大きな別れのために練習をしているんじゃないかなとも考えましたね。

── かつてロロ、三浦直之を象徴するフレーズは「meet」だった。自然とそれを卒業して、meetのあとの時間をどう過ごすかにシフトしたのかもしれませんね。
三浦 ああ、確かにそうですね。別れもそうだし、一緒に過ごす、一緒に暮らす時間を描いていきたいと思うようになっている気はします。
── でも『四角い2つのさみしい窓』で描かれている、一緒にいる、という関係はどれもトリッキーですよね。物理的な距離は近いのにお互いの認識がかなり俯瞰というか。男女の心理戦って、普通は自意識の陣地取りみたいになると思うんですけど、そういった駆け引きではなくて、嘘をつくにしても、もっと大きなものに対してというか。
三浦 固有の関係性のレッテルを剥がすことは、最近ずっと取り組んでいることだし、いろんな物語を読んだり観たりしても、そういう作品が増えてきていると思います。僕としては、レッテルを貼り続ける、レッテルを張り替えたり上塗りする、それによって逆にレッテルを剥がしていきたいんです。最終的には溶かせたらいいなと思います。
── 「溶かす」はせりふとしても出てきますね。それと、レッテルの貼り方、剥がし方にもいろいろありますが、ロロは、したほうにもされたほうにも悪意が感じられないのが特徴だと思います。もとの状態が嫌いだからレッテルを剥がすといったネガティブから始まっていない。
三浦 それはやっぱり僕が、主宰、脚本家、演出家だということをどうやって乗り越えていくかと関係していると思います。たとえばこういうインタビューでロロについて「疑似家族的にしたい」と言うこと自体をもうおしまいにしたいと最近は思っていて。
── 鳥公園のステイトメントと同じようなことでしょうか?
三浦 はい。西尾(佳織)さんが始めたのは、すごく素敵な取り組みだと思います。あの話にならうと、劇団の中の父(の役割)が分散されていくのが良いと思っていて。僕は、自分は劇作家で演出家という自負もあるけど、俳優も演出家だと考えているし、僕には僕のポテンシャル、俳優には俳優のポテンシャルを発揮できる場があるはずなんですよね。それを形にするには、父のレッテルをみんなで付け替えていくのが良いんじゃないかと。誰かが父で、ある時には僕が母だとか、別の誰かと誰かが兄弟とか、役割をぐるぐる流動させて、それによって権力を剥ぎ取ることができないかなと考えています。

── 『はなればなれたち』上演前のインタビューでは、劇団の存続の意味を探っていらっしゃる印象でしたが、今のお話でその答えを聞けた気がします。と同時に新作の内容とぴったり重なっていますね。
三浦 これはあくまでも僕の考えですけど、劇団の中のレッテルが溶けていった先に、メンバーの言葉がもっと外に出ていく機会が増えて、僕の言葉と同じくらい多くの人に共有されるようになっていけばいいなと思っているんです。
── その新作『四角い2つのさみしい窓』、タイトルはそのまま、ロロのことですよね。「ロ」という字を窓に見立てて。
三浦 タイトルは(内容より)だいぶ早く出さなきゃいけないので(笑)、何かすごく深いことを考えて決めたわけではないんです。ただ、メンバーだけでつくるし、ロロを象徴するタイトルにしようと。そこから窓というワードをストーリーの中でも扱おうと考えていきました。
でも最初、演劇のモチーフとして窓はすでに相当使われているから、そのまま出してもあまり新しいことはできないなと。それで、誰かと誰かを分ける壁があって、その壁が透明になったら窓になる、その時にどういうことが起こるかだろうと考えていきました。今回、防潮堤が一瞬出てくるんですが、防潮堤が窓に変わったら「海が見える!」と歓迎されると思うんですよね。でも、窓は向こうが見えても触れないじゃないですか。そこから触るということを考えていき、iPhoneのスクリーンとかも窓だとしたら、窓そのものに触る機会が、実は僕達ってめちゃめちゃ増えている。そんなところもイメージを膨らませていきました。
── 窓を隔てて触れ合うことと、窓を開けて触れ合うことは違いますが。
三浦 すごく抽象的な言い方ですけど、あっちとこっちを分ける窓があるとして──それは嘘と本当でもいいし、男と女でもいいんですが──、その窓を道に変えたいんです。何かと何を隔てる線、壁、窓といったものを、みんな道に変えて進んでいきたい。そうするとこっち側とあっち側が溶けて、こういう(二次元の)対立の構図だったものが、まったく違うこういう(三次元の)視線を持てるんじゃないかと。
── 前述の「溶かす」はそことつながっているんですね。それが舞台上で見られるのが楽しみですけど、それにしても三浦さんが目指すそのイメージは、人類規模の対立の解決策になりそうな大きなものでは?
三浦 実はこの1年ぐらいで書けないものがどんどん増えているんです。それは去年NHKで脚本をやらせてもらった『腐女子、うっかりゲイに告(コク)る。』っていうドラマがすごく大きい経験だったんですけど。
── あ、コンフィデンスアワード・ドラマ賞の脚本賞、おめでとうございます。
三浦 あ、ありがとうございます(笑)。つまり当事者という問題が、自分の中でどんどん大きくなっていったんです。『腐女子、うっかりゲイに告(コク)る。』の原作の作者の浅原ナオトさんは同性愛者で、一人称であの小説を書かれていて、純という主人公の男子高校生には浅原さんの気持ちがすごく乗っかっているわけです。それを自分が脚色する時に、どう関わっていくかすごく悩んだんですね。非当事者が言える、当事者が抱えている問題は、どんな言葉にできるんだろうと。と同時に腐女子の問題もあった。僕はBLのマンガも読みますけど、女子でもないしBLがすごく好きという人間でもないから、そのキャラクターもどういうふうに描けるかも考えて……。
それで、純君のせりふには僕は一切手を入れないと決めたんです。純君の悩みを「自分も思春期の頃の人に言えない悩みがあった」という経験と結び付けて普遍化することは、一番やっちゃいけない行為なんじゃないかと。一方で、腐女子の三浦さんのキャラクターは、僕もああいうふうにカルチャーを愛して、そこから生まれた想像力が誰かを救うのはすごくわかるから、どっちかと言えばそっちに自分を置いてみようと考えました。
浅原さんが自分を託した純君がいて、僕という人間を乗せた三浦さんがいて、それが出会っていくことを考えて書きました。それでもやっぱり、番組を観た腐女子の方の中には怒る方はいましたけど。僕もすごく資料を漁りましたけど、漁れば漁るほどグラデーションが半端なくて、ここでオッケーという方もいれば、まだまだダメという方もいましたね。
── 単なる趣味と片付けられない、デリケートな問題ですね。
三浦 すごく良い経験をさせてもらいました。やっぱり何かを書けば誰かを傷付けることは引き受けなきゃいけないんだなと改めて実感しましたから。
その時にすごく考えたのが、僕は実感としてわからないことをこうして書くけど、俳優はわからないことを演じられるのかな、ということでした。そうした俳優の負荷も考えて、誰かを傷付ける可能性も引き受けて、その上でどういう言葉を書くか……。そのためにはもっともっと勉強していこうと思ってはいるんですけど、それでも人を傷付けることがめちゃめちゃ怖くなっているのも事実なんです。だから今、どうやって当事者、非当事者を超えていくかが自分の中で大きな主題になっていて、それがたぶん、どうすれば「溶かす」ことができるのかにつながっているのかなと思います。
── 私、一昨年から去年にかけてしきりに「弱いい派」という流れが演劇界にあると言っていたんですけど、それも当事者と非当事者の問題を根本に含んでいます。
三浦 それで女性のせりふを書くのがすごく怖くなっているんですよね、僕。もはや僕が複数出てくる物語しか書けなくなるんじゃないかって、本当にこの1年悩んでいます。小説家だったらまた違うんでしょうけど、演劇って俳優がいて、ロロのメンバーには女性もいるから。今のところ、僕が自分はひとりだという限界をまず受け入れて、それに対して俳優が僕が書いた言葉を言ってくれることを期待して、つくっていくやり方を信じるしかないんですけど。
── 10周年イヤーの締めくくりとして2本の劇団公演があり、ちょうどそのタイミングで板橋さんがブレイクし、三浦さんも脚本の賞を獲られた。前作のインタビューでは「劇団以外の仕事も、ロロのためになるものを選ぶ」とおっしゃっていましたが、その点で実りのあった1年が終わろうとしています。今後のことはどんなふうに考えていらっしゃいますか?
三浦 ロロで作品をつくるのがやっぱり1番楽しいなって、今、珍しく心から感じているんです。矛盾するようですけど、「ロロを続けたい」といった気持ちから解放されつつあるというか。良い意味で、めちゃめちゃ続けたいけど「みんなと一緒にいたい」という呪いからは自分を解放しつつある。メンバーみんなもそうあって欲しいと思いますし。だから自分の中のひと区切りがついて、集団をテーマに描くことはとりあえずこれで終わりになると思います。
今後ですけど……、さっき言われた「悪意がない」問題、単純に僕は書けないんですよね、なぜかはわからないんですけど。今までもやってはみたんですけど、わかりやすい紋切り型の悪役みたいになってしまう。制作とこれからのことを話していた時に、まさにその部分、人間の悪意とか暴力をモチーフに作品をつくっていきたいと話をしたところです。次の作品は楽しいロマンチック・コメディになる予定ですけど、その先は、「書けないことを書けるようになる」を目標に、まったく違う作品を目指すかもしれません。
インタビュー・文/徳永京子
ロロ『四角い2つのさみしい窓』公演情報は ≫コチラ