【連載】ひとつだけ 徳永京子編(2017/04)― 【タニノクロウ作・演出】Mプロジェクト『MOON』
ひとつだけ
2017.04.28
あまたある作品の中から「この1ヶ月に観るべき・観たい作品を“ひとつだけ”選ぶなら」
…徳永京子と藤原ちからは何を選ぶ?
2017年04月 徳永京子の“ひとつだけ” 【タニノクロウ作・演出】Mプロジェクト『MOON』
2017/4/29[土]~5/3[水祝] 静岡・舞台芸術公園 野外劇場「有度」
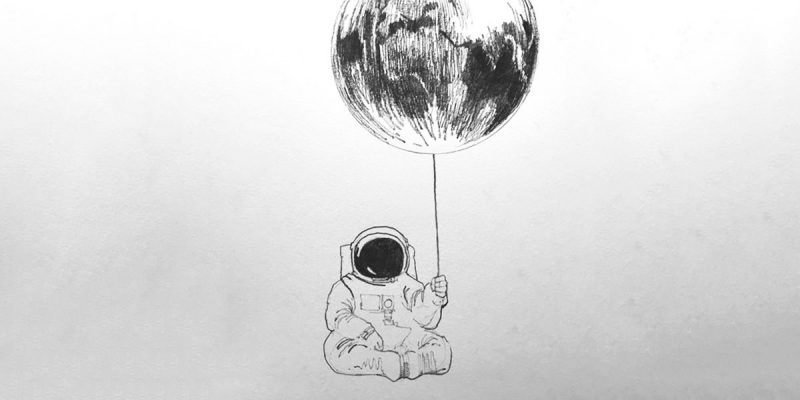
もう初日が開いてしまうし、早々に前売りが完売して、あとは少しのキャンセル待ちしかチケットの入手方法がないそうなので、こうして採り上げることが憚られるが、やはりタニノクロウの新作には格別の興味が湧くし、『MOON』についての構想を聞いて、その興味はさらに大きなものになったので、ここに書いておきたい。
タニノの作家性は複雑だ。「元・精神科医」というキャッチーな肩書きを持つ演劇作家が、性的な深層心理が生む悪夢のような、あるいはヨーロッパをルーツとするダークなおとぎ話のようなビジュアルの舞台をつくり、しかもそこで使われている男根型のオブジェを自ら作成しているというスペックは、わかりやすいストーリーがなくても、多くの人の気を引く派手さを持っている。その流れを具体的に汲む『苛々する大人の絵本』や『大きなトランクの中の箱』は、タニノ及びタニノ率いる庭劇団ペニノの代名詞と呼んでもいいだろうし、実際にヨーロッパ各地の劇場や演劇祭で人気を博している。
だが、そんなふうに、頭の中にあって現実にはない不思議な世界を現前化することだけがタニノの特徴ではない。
まず、場所に対する非常に強いフェティシズムを持っている。2004年の『黒いOL』では、新宿の空き地にテントを張り、地面を掘って長い水路をつくり、ほとんど洞窟のような劇場をつくった。また、タニノの祖母が暮らしていたマンションを(数年後に建て替えが決まっていたとはいえ)自分たちで柱を切り、壁を抜いてアトリエはこぶねをつくって、作品によっては客席1席ずつをパーテーションで区切って観客が個室で作品を観るようにするなど、継続的に改築を続けた。また昨年、10年ぶりに再々演した『ダークマスター』は、舞台上のセットはそのままだったが、公演先ごとに客席の美術に趣向をこらしたと聞く。おもちゃを解体しては夢中になってカスタマイズする子どものように、既存の場所に執拗に手を加えるのだ。
さらに、昨年の岸田國士戯曲賞を授賞した『地獄谷温泉 無明ノ宿』、ドイツのクレーフェルト劇場に委嘱されて作・演出した『水の檻』は、前者が開発の波に押されて消え行く土地とそこで生きる人、後者は福島第一原発事故にショックを受けたドイツ人の精神の変遷と、いわゆる物語を丁寧に書く劇作家タニノクロウも、近年は活躍を始めた。
上記のような複数の特性は、それぞれが孤立して特定の作品と結びついているのではなく、作品によって割合を変えながら含まれていて、少し離れたところから見れば、さほど違和感のないことなのかもしれない。それをわかっていてもなお新鮮に感じられたのが『MOON』についてタニノが語った言葉だ。
ウェブカルチャーマガジンのCINRAで『MOON』が上演される「ふじのくに⇔せかい演劇祭2017」について、主催者であり上演会場となるSPAC(静岡舞台芸術センター)の芸術監督である宮城聰と 対談してもらった 際、タニノからはとてもポジティブな空気が感じられた。
宇宙服のような、頭部を丸ごと覆うヘルメットを観客がかぶって参加するという作品を説明する際に、作者として自分がしているのは「夢を見ている」ことだとタニノは語った。寝て夢を見る状態を指しているのではない、いわゆる、明るい未来を夢見るほうの意味で。片や宮城は、世界が日に日に不寛容になっていることに強い危機感を示し、多くの人はそちらに頷かざるを得ない状況なのに。
ならばタニノが生来の楽天家かと言えば、そうではない。精神科の臨床医として現代社会が人間をどれだけ苦しめているかを多数、目の当たりにしてきたし、過去の作品には現代人が感じている抑圧や苦痛が扱われてきた。ところが新作では「演出というより夢見ている」のだと言う。
その変化についてタニノは、『水の檻』で出会い、『MOON』で再び組むドイツ人舞台美術家のカスパー・ピヒナーとの協働が大きいと話してくれたが、理由が非常に興味深いのだ。CINRAの記事にも書いたが、ピヒナー氏との会話は英語を使うのだが、動詞の過去形を思い出したり調べたりするのが面倒なので、そのままか、動詞を変化させなくてもいい「will」を使って話すことが増え、結果、未来志向の話しかしなくなったことが、意識を変えていったそうだ。
嘘みたいな話で、最初はタニノ得意の真顔で言う冗談かと思ったが、そうではなかった。しかし確かに、話すことが思考を決めていくのはよくあることで、だとしたら『MOON』は“未来形の会話によって考え方が前向きになった人間がつくる舞台作品”という側面があり、それだけでかなり惹き付けられる。
もちろん肝心なのは「何について夢を見たか」だが、それも「相手の国籍や年齢や性別がわからなくても一緒に同じ目標に向かえるか」という、世界平和の最初の目標に出てくるような素朴な、しかし、今最もセンシティブで危険とも言える問題についてだという。
これには前段があって、一昨年、カントール生誕100年を記念して、東京芸術劇場で『タニノとドワーフたちによるカントールに捧げるオマージュ』というワーク・イン・プログレスが上演されたのだが、これは、小人症の俳優たちが観客を巻き込み、暗闇に包まれた会場からドワーフ(小人)たちが明るい外へと出ていくのを協力し合って手伝うことを成功させた祝祭劇だった。
出演者がほぼ同じこの作品が『MOON』のベースだが、観客はヘルメットを被るだけでなく、さらに積極的な作業をすることになるらしい。それがどんなことはかは、幕が明けてからのお楽しみとなる。
たとえ劇場で隣り合って、その時は心を合わせて一緒に作業をしても、その点の時間が線や面になる可能性は、とても低い。そう簡単に世の中は良くならない。そんなことはみんな知っている。
けれど、学生時代からずっと自分が手がけてきたこだわりの美術を、初めて他人に託すことになり、その相手は言葉の通じないドイツ人で、ふたりであちこち散歩をしては、つたない英語で「この葉っぱの色が好きだ」「今日の夕陽はきれいだ」「このコーヒーは美味しくない」というすり合わせをひたすら積み重ね(2015年、『水の檻』を終えて帰国したタニノが、アーツカウンシル東京主催のパブリックトークで話していた)、次の作品でも美術を自分以外の人間に任せられるようになったタニノが、さらに未来志向になってつくった作品の、人を変える可能性は誰にも否定できない。
そこに小さな希望を抱くことは、演劇を観る者に許された、ギリギリの楽観主義ではないか。
≫ 【タニノクロウ作・演出】Mプロジェクト『MOON』 公演情報は コチラ



