【連載】ひとつだけ 藤原ちから編(2017/03)― 悪魔のしるし『蟹と歩く』
ひとつだけ
2017.03.10
あまたある作品の中から「この1ヶ月に観るべき・観たい作品を“ひとつだけ”選ぶなら」
…徳永京子と藤原ちからは何を選ぶ?
2017年03月 藤原ちからの“ひとつだけ” 悪魔のしるし『蟹と歩く』
2017/3/25[土]~3/26[日] 岡山・倉敷市立美術館講堂
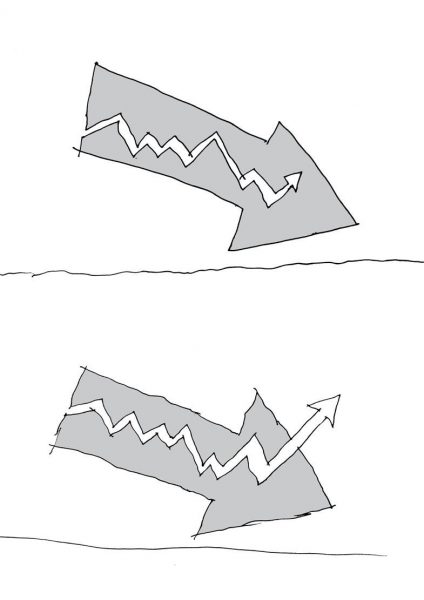
『蟹と歩く Walking with Cancers』と題されたこの公演について書くにあたって、悪魔のしるし・ 危口統之氏の病 に触れないのは不自然であるだろう。しかしそれを書いた瞬間に、本人をはじめ、彼を支えている周囲の人たち、そして彼の多くの知人や友人たちのあいだで生まれている暗黙の連帯を裏切ることになるかもしれない。思い出されるのは、病を公表してすぐの彼の言葉である。
このたびのことで誰かや何かが恨まれたり不幸になったりしてはいけない。それは俺が許さない。そして俺の身に起きた出来事、俺の癌は俺のものだ。だから盗むやつも許さない。いたら注意する。(*1)
この言葉はわたしを救うと共に、呪縛としても機能した。このおかげで、ちくしょう、俺はおめおめと生き延びてやるぞ……となんとか思うことができた一方で、病と死という、人間にとって欠くべからざる要素について、ほとんど何も書けなくなってしまった。ごく親しい友人と彼の話をするのはいい。問題は文章だ。何を書いても、そのイメージは彼の病へと結びついてしまう。それは「盗み」なのか。そもそも文章を書くという行為自体が、少なからず他人の人生を「盗んでしまう」ものではないか。その事実を今さらながらに突きつけられた気がして、どうしていいかわからなくなった。
なのに、編集部から「今月の『ひとつだけ』は何にしますか?」と訊かれた時、わたしは「悪魔のしるしの『蟹と歩く』にします」と即答してしまった。他にも気になる公演はあるはずだが、『蟹と歩く』をスルーすることは考えられなかった。これは独り善がりなオブセッションかもしれない。でもこれを避けて通ったら、自分にはもう、何も書けないだろう。
正直ついでに吐露すると、このコーナーは建前としては「演劇の紹介記事」である。にもかかわらず、わたしはこの倉敷での公演に、例えば初めて悪魔のしるしを観るような人々がどやどやと押しかけることを望んではいない。悪魔のしるしのメンバーがこの公演の実現に向けて尽力しているのも、多くの新規の人に観てもらいたいとかいうより、「危口さんの最後の望みを叶えたい」との想いのほうが強いのではないかと勝手ながら推察している。実際、親しい知人・友人や、これまで悪魔のしるしを観続けてきた観客たちが倉敷に集まるだけでも、かなりの人数にのぼるだろう。だから「紹介」する必要はほとんど感じられない。
しかしこの『蟹と歩く』が、限られたメンバーによる私的で排他的なパーティではなく、あくまでも「公演」としてひらかれているということ。わたしはそこに何か希望のようなものを感じているのだった。「体力の低下」という事情により、危口氏のクレジットが「作・演出」から「原案」に変更されたとはいえ、残された力の多くを、彼がこの「公演」に注ごうとしているのは間違いない。ではなぜ、彼は「公演」を打つのだろうか。そもそも彼はなぜ、演劇をやるのだろうか。
*
危口統之(悪魔のしるし)は、「搬入プロジェクト」や「百人斬り」といったシリーズによって、演劇というジャンルを超えたポピュラリティを獲得してきた(かなりの動員数を記録しているはず)。他方で、彼は多くの奇妙な演劇作品を創作・発表し、独特としか言いようのない存在感を築き上げてきた。
今思うと、『悪魔のしるしのグレートハンティング』(2010年)がひとつの分水嶺であり、彼らの数奇な旅の始まりでもあったのかもしれない。本人はこの作品のせいで「内なる声」が全く聞こえなくなったと 振り返っている が、おぼろげな記憶によれば、フェスティバル・ディレクターに扮した女優が舞台に現れ、アーティストを演じる男優に作品をつくるよう依頼する、ところが彼ときたらゴミのようなものをつくるばかり……という筋書きだったと思う。ここに芽生えていた一種の反発心(?)のようなものは、その後の『桜悪魔の園しるし(SAKURmA NO SONOhirushi)』(2012年)や『倒木図鑑』(2013年)にも引き継がれ、「助成金」や「劇場」といったシステムに対する、彼自身の自虐・自爆を含んだアイロニカルな態度へと繋がっていった。

『悪魔のしるしのグレートハンティング』 撮影:杉田大輔
彼は毎回、真剣に創作に取り組みながらも、最終的には「演劇」であることに「失敗」し続けてきた。あと少し、最後のピースさえはめれば「演劇」として多くの人々が納得するぞという時に、悪魔の仕業なのか何なのか、そのピースはどこかへ持ち去られてしまうのだ。『倒木図鑑』あたりでは大いに怒った人もいたようである。けれどもわたしは彼のこの態度をどうにも憎むことができない。『禁煙の害について』(2010年)のような、構造的にもシンプルで切れ味の鋭い作品をつくり続けていれば、それはそれで人々を苛立たせたにしても、もう少しわかりやすい「評価」とそれに伴う名声を手に入れていたかもしれない。しかし危口統之=悪魔のしるしはそうしたクレバーな道を選ばなかった(選べなかった)。だからこそ、アンコントローラブルな実の父親を舞台に召喚するという『わが父、ジャコメッティ』(2014年)のような不思議な作品も生まれたのだろう。
ともあれ悪魔のしるしは、2017年に至ってもなお、「演劇界」からアウトサイダー的な扱いを受け続けている。逆に彼らからしてみれば、勝手に「演劇界」に取り込まれてもな……という感じかもしれないけれども。制作の岡村滝尾氏は、その「困惑」について次のように表現している。
「演劇をプレイし続けていた結果、『演劇』の認定印を押されるところまで近づき、そして、困惑しながらもあがく事を止められない悪魔のしるし」(*2)
危口氏の群を抜いた知力にもかかわらず(演劇にかぎらず現在生きているアーティストで、彼に匹敵できる人はそうはいないだろう)、悪魔のしるしは、およそクレバーさからはほど遠い振る舞いを続けてきた。悪魔のしるしの公演の帰り道では、批評家やプロデューサーが「またか……」と嘆く声を、わたしは幾度となく耳にしたものである。けれどもそこには「まあそれが危口君らしいんだけどね……」という温かな諦観も少なからず含まれているようではあった。なんにしても悪魔のしるしは愛されてきたわけだ。それは危口氏が毎回ミイラに扮したりなんだりしながら地べたを這いずり回っている、その姿が愛おしいせいでもあるだろうが、それだけではない。何かもっと遠い遠い極点を、そして大海のようにひろがる〈巨視的な時間〉を彼は見てきたのだった。そしてその前人未到のヴィジョンが、何か得体の知れないものを生み出すかもしれないと、わたしは、観客は、信じ続けてきたのである。
例えば何度か彼は、シモーヌ・ヴェイユの『重力と恩寵』に言及してきた。34歳の若さで死に至った彼女の壮絶な人生とその思想について、ここで詳しく解説することはわたしにはできないが、もしかすると、一時期は工場労働者にもなったヴェイユの人生に、肉体労働者として長い時間を過ごしてきたみずからの姿を、彼は重ねてきたのかもしれない。とにかく危口氏は、彼女の思想の鍵概念である「真空」に興味を持っているらしい。キリスト教の強い信者であるヴェイユは、人間を俗物的な下降へと誘う「重力」と、神からの「恩寵」とのはざまに、その「真空」状態を見た。言い換えれば「真空」とは、神がいなければありえない状態であり、信じる神を失った人間にはとても耐えられないような、恐ろしい、究極の孤独ではないだろうか。おそらく無神論者であるだろう危口統之は、この「真空」という言葉にどんなイメージを重ねているのだろう。
思い起こされるのは、昨年、美術ライターの島貫泰介氏のキュレーションで創作された『劇的なるものをネグって』(2016年)である。小さなギャラリーでの上演ということもあり、観客は全部で178名のみだったそうだ(島貫氏のtwitterによる)。この作品において危口氏は、およそ2500年におよぶ演劇=劇場の壮大な歴史を紐解いて年表をつくり、会場で展示した。一方で、そのへんの公園や広場に放置されている「残念舞台(舞台らしきもの)」の情報をかき集めたのだった。そしてあろうことかパフォーマンスの終盤で、彼はみずからの4本の手足に長い柱を取り付け、「残念舞台」そのものに変身してしまったのである。

『劇的なるものをネグって』(2016) Photo by Hideto Maezawa
「演劇」の「正史」から取りこぼされた「残念」な存在。重力に逆らうこともできず、おそらくは信じる神も持たず、劇的であるという「演劇」の最後のピースさえも拒絶して舞台に大の字に寝そべった彼は、全身でその「残念」さそのものになっていた。ユーモラスな作品でもあり、わたしは爆笑しながらその変身の一部始終を見ていたのだが、なぜか、彼が天に向かってその4本の手足をゆらーっと差し出す姿を見た時に、不意に、涙が溢れてきた。あれは……なんだったのだろう? わたしは何に感動したのだろう。わからない。以下に言葉にしてはみるけれど、これはとりあえずの仮説でしかない。
……この世に人間(木口統之)として生まれ落ちたにもかかわらず、「演劇」という、死者たちから連綿と手渡されてきたバトンをうっかり引き取ってしまい、悪魔のしるしと称して、その宿命を演じ続ける者(危口統之)。そのかなしみ、よろこび、そしてみずからの存在意義への〈祈り〉のようなもの……
何もかもが無限であると勘違いをして、わたしは、ひとつひとつの貴重なチャンスを蔑ろにしてきたように思う。先日、TPAMの会場に彼が車椅子で現れた時も、わたしにできたのはただ、1枚の写真を撮ることだけだった。写真の中の彼の目は、いつものように虚空を見つめるばかりで、何らかの意味や感情を、読み取ることはできない。
*
「なにか劇をやるというよりは なにかを劇にする なにかが劇になる あるいは 劇をなにかにする みたいなことばかりやっている」 (*3)
*
本番前のいつもの状態だが、
「今度こそもう終わりだ」と思わざるをえない。
それは
「これで演劇をもうやめよう。向いてない」
でもあるし、
「こんなクズなのは止めて、やるのならちゃんとやろう」
でもある。
毎回毎回、こうなる。不快だ。
好きなことをして生きていける星の下に
生まれたかった。(*4)

『劇的なるものをネグって』(2016) Photo by Hideto Maezawa
—————
(*1)2016年12月7日の危口統之(@kigch)のtwitter https://twitter.com/kigch/status/806355578050121728
(*2)「悪魔のしるしによる、悪魔のしるし解説」2014年 http://kyoto-ex.jp/2014/feature/16975/
(*3)同上
(*4)2016年7月25日の危口統之(@kigch)のtwitterにポストされた手書きの文字を筆写したもの https://twitter.com/kigch/status/757583482226749440)
≫ 悪魔のしるし『蟹と歩く』 公演情報は コチラ



