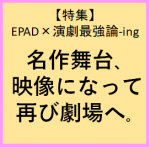【配信作品レビュー】ブルーエゴナク『眺め』
名作舞台、映像になって再び劇場へ。
2024.02.19
2023年度にEPADが収集した舞台作品のうち、121本が配信可能になる。語り継がれる名作舞台から、最新の若手の意欲作まで、多様な舞台が映像で見られるようになる。そのリストから1本を選んでもらい、レビューを書いてもらう「配信作品レビュー」。本稿のレビュアーは、演劇ジャーナリストで本サイトの運営者である徳永京子が務めます。
* * *
さまざまな時間軸を行き来しながら描き出す、避けられない大きな絶望──ブルーエゴナク『眺め』
Text:徳永京子(演劇ジャーナリスト)
■3都市を拠点とする劇団 コロナ下でのクリエーション

『眺め』の一場面(撮影:岩原俊一、平田歩海)
昇っていたはずなのに、気が付くと下にいる。降りているつもりが、いつの間にか高い場所にいる。「ペンローズの階段」と呼ばれる、だまし絵のような四辺の階段のイラストを目にしたことがある人は多いだろう。ブルーエゴナクの『眺め』の舞台セットは、まさにこの階段を思い起こさせる。階段になっていない辺もあるので厳密にはそう呼べないのだが、昇っているのか降りているのか、つまり、進んでいるのか戻っているのかわからなくなる運動がこれからここで始まることを、物語の口火が切られる前に装置が教えてくれる。果たして『眺め』は、過去にも未来にも長く高く延びた、遥かな時間を描いた話だった。
ブルーエゴナクは、もともとは福岡県北九州市を拠点にしていたが、現在は京都と東京を加えた3地域で活動する劇団で、メンバーは9人、作・演出を主宰の穴迫信一が担う。『眺め』は2021年10月に、北九州芸術劇場小劇場と京都のTHEATRE E9 KYOTOで上演された。穴迫が積極的に音楽制作をしているのをSNSでの発表で知ったり、複数の土地を軽やかに移動というよりは、それぞれの土地でしっかり腰を据えて創作をしている集団という印象があり、作品を観てみたいと思っていたのが、この機会にかなった。
劇団のHPにある、『眺め』の上演に際して書かれた穴迫のメッセージを抜粋すると「多くの人が様々なものを失った2020-2021において、手段と目的を行き来する「演劇」という抽象的な存在を、時に憎しみ慈しみながら、自分が獲得したものの一つは〈声〉への信頼です。」とあり、さらに解説には「「声」がいかなる形式で上演性を担保し、舞台上に存在する生身の俳優や観客に対して、どのような影響力を持ってその場所に響くかを検証します。」とある。
実は、創作上の重要なコンセプトである上記の声に関する説明を筆者が知ったのは、最初にこの作品を観たあとだった。そして小さくない戸惑いを感じた。声がそれほど大事な役割を果たしていたとは思えなかったのだ。もっと正確に書くと、確かに何ヵ所で流れた録音の声は印象的ではあったけれど、それを抜きにしても『眺め』は、複数の方向から緻密に練り上げられた、見応えのある作品だったからだ。
「過去編」と「未来編」に分かれた物語は、「日差し」(木之瀬雅貴)という名の18歳の青年が、突然、ガールフレンドの「森ちゃん」(小関鈴音)に振られるところから展開していく。「日差し」は、バイトもせずに昼過ぎまで寝ている呑気な生活を送っているが、「森ちゃん」は地道に将来のための計画を立てるしっかり者だ。思いつきや驚きをすぐさま大きな声で出せる「日差し」に対して「森ちゃん」は、子供の頃に母親と観覧車に乗り、降りてきたら待っていたはずの父親が失踪していた過去があり、その影響か、感情や言葉をあまり外に出さない。そうした各々の性格や境遇を伝える短いシーンが、もうそれだけで良い感じなのだ。スタスタと歩く「森ちゃん」、必死で追いかける「日差し」、何度か繰り返される「森ちゃん!」「なんや?」のリズムで、ふたりがこれまでに過ごしてきた平凡で最高な時間が一気に想像させされ、簡単には別れてはいけないふたりであることがくっきりと印象づけられる。
「森ちゃん」との関係を挽回し、何より、どうしても言いたいひとことがある「日差し」は、自覚のないまま自室の片隅を棲家として提供し、いつの間にか鞄の中に入っていたアシダカグモ(声:菅一馬)の力で、指先をスクロールするように動かすだけで時間移動が出来るようになる。そして手遅れにならない時間軸を求めてタイムスリップをするうち、顔も名前も知らないのに懐かしいひとりの女性に出会う。その女性、「春望(はるの)」(平嶋恵璃香)もまた時間を行き来しており、「森ちゃん」と深い関係にあった。
「過去編」は主に「日差し」のタイムトリップ、「未来編」は主に「春望」のタイムトリップが描かれていくのだが、離れた時間を紡いでいくストーリーは複雑で、筆者には完全には理解しきれないところもあったが惹きつけられ、何より、演出に唸らされた。
「森ちゃん」のイマジナリーフレンド的な存在であり、「春望」と深い友情を結ぶ「ノミ」(野村明里)という女性がいるのだが、他の登場人物が長方形に区切られた道や階段を立って歩いたり走ったりする中で、唯一、ほとんどの移動を横たわってする。そして「春望」との会話の中で「あなたを基準に前と後ろが分かれる」と話すのだが、多くの時間を寝た姿勢を取っている彼女がそう話すことで、前後左右で構成されていた『眺め』の世界に、上下の概念が持ち込まれ、それまでとは異なる広がりが生まれたのだ。それは、無数の時間軸に刻まれていた世界が、一気に宇宙空間を獲得した、目の覚めるような瞬間だった。
■物語に差し込まれるモノローグ 別々の時間軸から響く複数の「声」

『眺め』の一場面(撮影:岩原俊一、平田歩海)
最初にここまでの感動がもたらされていたので、作・演出家の声へのこだわりに触れた時にかえって戸惑いを感じ、もう1度観直した。そしてようやく、声がこの作品に埋め込まれた重要なピースであることに気が付いた。
最初に流れる女性のモノローグ、落ち着いて温かいその声(重実紗果)は、最初は詩を読んでいるのかと思われるのが、よく聞くうち、彼女の孫が幼かったある日の思い出を話しているとわかってくる。公園の恐竜の遊具から滑り降りてきた祖母に驚いた4歳の「日差し」が全速力で逃げていく、その愛らしい姿について語っているのだが、その遊具が恐竜であるところに大きな意味がある。観客の脳内に確かな映像を喚起させる重実の声で、何億年も前に地球に生息した生き物のイメージが耳から流し込まれた時から、この作品の年表はスケールを大きく広げられていたのだ。
また、失踪した「森ちゃん」の父親(声:日髙啓介)が残したカセットテープの曲は、片方ずつのイヤホンで、「春望」と「ノミ」にシェアされ、やがて、「春望」が前向きに生きていくメッセージを生み出す。
さてここで、他の登場人物の誰とも言葉を交わさず客席に向かってひたすらモノローグを話す、「せかい」(高山実花)という名の人物について書かなければならない。他の人物が横移動、あるいは四辺をぐるりと回って移動する中、舞台奥から出てきて帰っていく、縦移動だけに終始する唯一の人物だ。彼女の話は自分の名前のこと、小さい頃に母親から阿修羅像に似ていると言われたこと、また、中学時代のある1日の思い出という他愛のないもので、「日差し」や「森ちゃん」や「春望」の物語との接点も無い。突然、「なんかいきなりすいません」と挨拶しながら客前に現れて、ブザーが鳴ると慌てて引っ込む彼女は、話の内容やトーンの軽さもあって、観客に近い立場の存在と感じられる。しかしやがて、彼女もまた時間の回廊に迷い込んだ経験があること、この世界に起きた決定的なディザスター、災禍の生き残りであることがわかってくる。そして、詳細が語られることのないそのディザスターが、この物語の始まりと終わりに決定的に位置付いていると気付かされる。
なぜ「せかい」は誰とも会話しないのか。劇中ではその答えは明かされない。勝手に考えるなら、肉体を伴ってはいるが、彼女もまた、この作品の中では“声”に位置付けられているのではないか。劇中で描かれる世界と交わらない、観客と地続きの存在。その人がディザスターを経験し、声を届けている。彼女は「日差し」達の世界ではなく、私達の世界に何かを言い残したくて、縦方向の近道を通って来たのではないか。だとしたら、彼女のような存在の“声”に気が付けるか──。
つくり手の狙いとはズレているかもしれないが、筆者にとって“声”は、作品が終わっても続く宿題になった。
—
徳永京子(とくなが・きょうこ)/演劇ジャーナリスト。朝日新聞に劇評執筆。演劇専門誌act guideに『俳優の中』連載中。ローソンチケットウェブメディア『演劇最強論-ing』企画・監修・執筆。東京芸術劇場企画運営委員。せんがわ劇場演劇アドバイザー。読売演劇大賞選考委員。緊急事態舞台芸術ネットワーク理事。著書に『「演劇の街」をつくった男─本多一夫と下北沢』、『我らに光を─蜷川幸雄と高齢者俳優41人の挑戦』、『演劇最強論』(藤原ちから氏と共著)。
視聴環境:ノートパソコンのモニターとスピーカー
* * *
ブルーエゴナク『眺め』
◆上演データ
作・演出:穴迫信一
出演:平嶋恵璃香、野村明里、小関鈴音、高山実花、木之瀬雅貴、日髙啓介、重実紗果、菅一馬
2021年
北九州芸術劇場小劇場(北九州)、THEATRE E9 KYOTO(京都)
◆作品を視聴するには
配信先 VideoMarket
配信中
※有料オンデマンド配信。事前に会員登録が必要です。
製作ノート 同劇団の作品としては、2022年上演の『バスはどこにも行かないで』が一足先に配信可能となっています。配信先等はEPADのサイトをご確認ください。