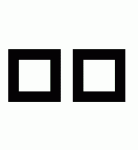新・演劇放浪記 第6回 ゲスト:坂本もも(制作者)
新・演劇放浪記
2016.05.25
新たな才能を次々と輩出してきた「小劇場演劇」が、たぶん今、何度目かの変革期を迎えている。その変化は現在どのような形で現れているのか。そして未来の演劇はどうなっていくのか?
国内外に散らばる演劇の現場の最前線。その各地で活躍する人たちを藤原ちからが訪ね、インタビューと対話を重ねていくシリーズ「新・演劇放浪記」。
第1回:岡田利規(チェルフィッチュ) 第2回:三浦 基(地点) 第3回:イ・ホンイ(翻訳家、ドラマターグ) 第4回:植松侑子(制作者、Explat理事長) 第5回:武田力(アーティスト、俳優)
* * *
2010年頃、小劇場で新世代の台頭が目に見えて起こってきた時、ロロと範宙遊泳という人気2劇団の制作者であった坂本ももは、まさにその渦中の人物であった。それから数年経った今、両劇団はそれぞれの道を歩んでいる。ボーイ・ミーツ・ガールの物語を得意としてきたロロは「いつ高」シリーズで高校生に向けた新たな展開を始めているし、範宙遊泳は文字をプロジェクションする手法をもって海外にその版図をひろげている。ロロ・三浦直之も範宙遊泳・山本卓卓も、劇作家としてそれぞれ岸田國士戯曲賞の最終候補にノミネートされ、共にその唯一無二の作家性は様々な世代から高い評価を受けるようになった。
しかし彼らの歩いている道はラクなものではない。その新しいスタイルは常に毀誉褒貶に晒され続けてきたし、(こう言ってよければ)ロロも範宙遊泳も実に多くの「失敗」を重ねてきたと思う。それだけ、誰もまだ踏み込んだことのない領域に、彼らは行こうとしてきた。その姿を、両劇団の制作者として、友人として、また妻として、坂本ももはどう見つめてきたのだろうか?
(2016年4月29日、都内某所にて収録)
▼ロロ・三浦直之との出会い
──今日は制作者としてロロと範宙遊泳という2つの劇団に関わっていること、そして海外での経験などお聞きしたいと思います。まず、ロロの制作をやるようになった経緯から教えていただけますか?
三浦(直之)くんは大学のひとつ上の先輩で友達でした。私はもともと演出家志望だったんですけど、大学2年から某学生劇団を演出助手で手伝うことになって、三浦くんはそこの制作だったんですけど、私が初めて手伝った頃には第1次三浦失踪事件っていうのが起きて、いなくなっちゃったんです三浦くん……
──ああ、噂の失踪事件が……(*詳しくは書籍『演劇最強論』の三浦直之インタビュー参照)
戻ってきて一度和解して、三浦くんが制作で、演出家と私が2本ずつ短編を演出する企画を進めてたんですけど、三浦くんが書いた『家族のこと、その他のたくさんのこと』が王子小劇場の賞(2009年佐藤佐吉賞最優秀脚本賞)を獲っちゃって、その公演が私たちのと日程どんかぶりで、オファー予定だった俳優はロロに出ることになり……。結局それで三浦くんは某劇団と絶縁状態になりました。旗揚げされたロロの公演(2009年5月)を観に行ったら、めちゃくちゃ悔しくて。だって三浦くんがいなくなったせいで迷惑こうむったのに、作品面白いしなんなのうぜーってなって、「三浦くんのせいだから!」って王子小劇場の階段で号泣しながら彼に言ったのを覚えてますね(笑)。ただ同時に「この人、才能あるんだな」ってことも思ったんです。
それから「15 minutes made」(6つの劇団が15分ずつの短編を上演するオムニバス)にロロが出た時に(2009年6月)演出助手を頼まれてやりました。旗揚げの翌月で現場の作法とか何もわかってなくて、結局主催と劇団のあいだに入る私が色々叱られることになったんですけど……。第2回ロロ本公演の『LOVE』(2010年1月)は演出助手兼制作をやって、人数合わせでちょっと出演もしましたね。
で、私自身、某劇団にはだいぶ尽くしたつもりだけど1円ももらったことないし、これ以上は続けられないなと思いながら、商業演劇の現場も経験させてもらってたから、蜷川(幸雄)組に行くかどうかこの先を迷っていた時期でした。だから、どうせやるならちゃんとやろうという理由で、劇団員としてロロに入りました。
──そこで「もう三浦くんとは一緒にやらない!」とはならなかったんですね。
思わなかったですね。ロロは当時私が最年少だったけど、上下関係もなくだいぶ言いたいことも言えました。でもどこかに「私はロロじゃないからここまでしかできない」とか「こんなにやってるのに私はロロじゃない」みたいなぎくしゃくした感じはあったんです。だからちゃんとメンバーとして責任持つ形にしないと、やっていけないなと思ったんですね。

ロロ『LOVE』
▼範宙遊泳・山本卓卓との出会い
──その後、範宙遊泳にも入るのは何がきっかけで?
……正直に申し上げますと、おつきあい先行です(笑)
──(笑)。そして(山本卓卓との)結婚にまで至ったわけですね。
範宙遊泳っていう劇団のことは当時知らなかったんです。よく知らないのに恥ずかしながら、同年代ではロロがいちばん面白い!とか思ってたんですよね。でも制作の赤羽ひろみさんと女優の佐賀モトキさんが立ち上げた「花ざかりのオレたちです。」っていう企画公演『三五大切』(2010年3月)に、ロロの望月綾乃が客演したんです。その脚本・演出が山本卓卓で、各大学のその年卒業するイケてるやつら(1987年生まれ)を集めて芝居やりますっていう企画でした。桜美林からは佐賀さんと、熊川ふみ、大橋一輝、大石憲くん、早稲田は高木健くんと清水穂奈美さん、青学が永島敬三くん、明治から大柿友哉くんと、なぜか年齢を勘違いされて呼ばれた金丸慎太郎くん(本当は1988年生まれ)、で、日芸から望月綾乃が出て、それを観に行ったんです。
──確かにかなりいいメンバーが揃ってますね。
その前に蜷川さんの現場で初めて会った大橋くんと、「日芸ならロロ知ってますか?今度ロロの人と共演するんですよ!」「え、あたしロロです!」ってやり取りをして、存在を知りました。観に行ったらすごく感動して、2回お金を払って観ました。同年代にこんなにいい役者いっぱいいるんだ、私の世界狭かったな〜っていう反省もあって、範宙遊泳の本公演も観てみようと。それが『ラクダ』(2010年7月)ですね。
──王子小劇場での公演ですね。僕もそこで初めて範宙遊泳を観ました。
たかくらかずきが手がけたチラシも作品もすごく良かったんだけど、お客さんがあんまり入ってなかったんです。「こんなに素敵なのにもったいない!」と思って、その次の『東京アメリカ』(2010年9月)も普通にお客さんとして観に行ったんですね。そうするうちになんとなくみんなと友だちになって……。山本とは2回くらい初日乾杯で喋ったくらいでしかなかったんだけど、色々あって(恋愛として)付き合うことになったんです。
──2回しか喋ったことなかったのに?!
あと「チケット取ってください」ってメールしたくらいかな(笑)。
──……で、付き合うことになり、次から制作に?
実は『ラクダ』を観た時に「制作やりたい!」ってツイートしてたんですよ。当時範宙は座付きがいなくて、山本が制作業務をしてるのを見てアドバイスしたり、こっそり手伝ったりしてるうちに正式にやってほしいと言われて、メンバーになったのは「20年安泰。」の『うさ子のいえ』(2011年6月)からですね。
──なるほど、若手世代の台頭の舞台裏でそんな恋が進行していたとはね……(笑)。でもいざ範宙遊泳もやることになった時、ロロの主宰である三浦くんは、掛け持ちすることを怒ったりゴネたりしなかったんですか?
しなかった……のはありがたかったです。ひとことだけ言われたのは、「ももちゃんの経験値としてもいいことだからやった方がいいと思う。でも、自分は誰かを好きってことを肯定して作品を書いてるから、もちろん作品が面白いからやりたいっていうことはあるにしても、卓卓くんが好きだからやりたいっていう気持ちを隠す必要はないと思うよ」って。
──いいこと言うね……(感動)
そう、いちいちいいこと言うんですよ、三浦くんは!(笑)

範宙遊泳『ラクダ』 撮影|雨宮透貴
▼新世代の制作者として
──とはいえ、2つの劇団を掛け持ちするのはそう簡単なことではないですよね?
そうですね……。ただハイバイやサンプルのお手伝いで、その2つの劇団の制作をされている三好佐智子さんの背中を見ていたというのはあります。
あと、ロロと範宙遊泳が世に出始めていく中で、「次の時代つくっていかなきゃいけないじゃん!」って周りの同年代から囃されたりもしたから。
──「私たちが次の時代をつくるぞ!」みたいな機運が同年代にあった?
あんまり深く考えずに飛び込んでしまったというか。同年代だけじゃなくて、岡田利規さんにも「制作者としても次の時代の人が出てきたね」って言っていただいたこともありました。
──傍目にも、2010年頃からロロ・範宙遊泳の坂本もも、マームとジプシーの林香菜という2人が、新世代の制作者として存在感を発揮し始めたと感じていました。
ZuQnZ(宮永琢生。劇団ままごとの制作)の存在は大きかったと思います。私は宮永さんを師匠だと公言してるんですけど。でも最初は(青年団制作の)野村政之さんに相談したんですよ。もともと私は蜷川さんの作品が好きで、小劇場にはそんなに興味なかったから、まったく勝手が分からなかった。それでロロの第3回本公演『旅、旅旅』(2010年5月)をやる前に、三浦くんが「どうやら野村さんっていう人が旗揚げ公演を観てくれているらしい。そして最近助手を欲しがっているらしい。ももちゃん飛び込んでみなよ!」って。いきなり助手になるつもりはなかったんですけど、まずはコンタクト取ってみようと思って、こまばアゴラ劇場の5階でやってた宣伝美術についての集まりに行ったんです。(『演劇公演の宣伝について考えるラウンドテーブル』2010年2月)
──あ、僕もそれ行った!
それでパネリストだった野村さんにその場で話しかけて、実はロロの制作をはじめたんですけど何もわからなくて、教えてくださいませんかってお願いして。後日あらためて、開演時間はこうやって決めるんだよとか、予算はこう立てるんだよとか、最近のこういう重要な人に会った方がいいよとか、丁寧に教えてくださって。「そういえば宮永琢生って人がいて、ちょうど明後日から人が足りなくて困ってるから行く?」と言われて、それで入ったのが劇団ままごと『スイングバイ』(2010年3月)の現場でした。そこに林香菜ちゃんもついていて。翌月にはやっぱりその時に知り合った三好さんからハイバイに呼ばれ、野村さんからサンプルに呼ばれ、FAIFAIを手伝ったり……といろいろ勉強しましたね。
──先輩制作者たちとのいい出会いがあったんですね。
次々に別の現場と制作さんを紹介していただいて、ありがたかったですね。
▼蜷川幸雄との出会い
──そうしていつの間にか若手制作者のホープと見なされることになったわけですけど……もともとは演出志望だったというお話でしたよね。自分が作家になりたいということへの未練はなかったんですか?
なかったですね。演出志望だったのも、蜷川幸雄さんが演出家だったからなんです。いつもそうだけど、私は誰か人を好きになってその人のために何かしたい、そしてその人の見てるものを見たいっていう、そういう思考回路なんですね。ロロも範宙遊泳もまさにそうですけど、その最初の入口が蜷川さんだったんですよ。とある作品に衝撃を受けまして……絶対演劇やりたいって思って進路変更したんです。それで日芸の演出コースに入りました。ただ、演出はやりたかったけど脚本書きたいとは思えなかったし、たぶん自分は違うんだろうなってことは薄々思ってました。
蜷川さんのそばにいたいから、蜷川組の稽古場に通ったり、お仕事させていただいたりしていた時期に、ロロが出てきて、同じように三浦くんのそばにいてみようって思ったんです。それくらいロロの世界は衝撃的だったんですね。今まで自分がこうだと思っていた演劇じゃなかった。蜷川さんの作品は、前提にちゃんとした物語があって、時空もそんなに飛ばないし、会話劇だし、感情が揺さぶられるようなお話……もちろんヘンなものが出て来たりはしますけど、いわゆる「お芝居」っていう概念がきちんとあり、それが素敵だなと思って演劇を観てきた。でもロロは「こんなのもアリなんだ!」っていうアイディアがいっぱい詰まってて……それを観た時に私にはこの観点で作品は到底つくれないと思ったんです。だからその人、つまり三浦くんのサポートに回るっていうことになりましたね。
──そもそも演劇は好きだったんですか?
好きでした。親がやってたんです。母親が東京キッドブラザーズのスタッフだったらしくて、2年くらいしかいなかったらしいですけどね。あと母親の親友が、あめくみちこさんっていう東京ヴォードヴィルショーの女優さんで、小学校2年生くらいから観に行ってました。父親もマスコミ関係だったり、祖母が工芸作家だったりしたので、演劇や美術や芸術が身近にありました。でも自分もやりたいとは思ってませんでしたね。最初はファッションの方に行きたかったんです、蜷川さんの芝居を観るまでは。高校1年生の時、嵐の二宮くんが出てたおかげで(笑)蜷川さんの『シブヤから遠く離れて』(岩松了作、2004年)を3回観に行きました。さらに自分も演劇やろうと思ったきっかけは、『天保十二年のシェイクスピア』(井上ひさし作、蜷川演出版は2005年上演)。あれは本当に凄くて、帰りの電車で母に「演劇やりたいんだけど」って言いました。

範宙遊泳『うまれてないからまだしねない』 撮影|雨宮透貴
▼ロロと範宙遊泳のライバル関係
──蜷川演劇との出会いが本当に大きかったんですね……。そうした出会いを経て、劇団制作者として7年目。2つの劇団を切り盛りしていく上で困難はなかったですか?
もうちょっとこれ以上は無理ですね(笑)。2年くらい前まではあんまり無理と思ってなかったんですけど、急に2人とも忙しくなって、スケジュールも被るようになってきたから。
でもいちばん困難なのは……正直に言うと、もともとロロの方が動員が多かったんです。名前的にもロロの方が先だった。意識しないようにはしてたんですけど、「ロロの坂本さんですよね。範宙遊泳もやってるんですか?」って言い方をされることが多かったし、それを聞いてる範宙のメンバーは若干気にしてるんじゃないかなってことは思ってました。三浦くんは映画も撮ったし、演劇以外のお話もちょくちょくもらったりしてたし。
それが、東京芸術劇場でやった『うまれてないからまだしねない』(2014年)で範宙遊泳の動員が倍になって、逆転したんです。それまではそもそもフルキャパ1000人未満の規模でしかやったことがなかったので、芸劇との打合せでも「動員1000人持ってないんですか?!」ってびっくりされたくらい。だからあの公演はチャレンジだったんですけど、そこからTPAM2014で一気に海外も決まったり、助成金も取れるようになったり、トントンと行ったことに対して、今度はロロの人たちが気にしてるかもしれないと…私がひとりで過敏になってただけかもしれませんけど。2つの劇団をやっていく中で、メンバーたちがお互いの劇団をどう思ってるんだろう、私が2つやってることに対してはどう思ってるんだろう、ってことは不安でした……。岸田國士戯曲賞に山本が先にノミネートされたことも、私はなかなかロロのメンバーに言えなかったので。
──仲がいいとはいえ、当然ライバル関係ではありますもんね。(季刊エス特設サイトの 対談 を参照)
山本は多分、悔しい気持ちもあったぶん2013年から2014年にかけて本当にストイックに創作に向き合って、それがひとまず報われたという気はしました。三浦くんが頑張ってなかったってわけではもちろんないですけど。
今は2人の作風も全然変わってきたけど、当時は同い年ひとくくりで比べられることも多かったので。
──じゃあ今後はもしかして範宙遊泳1本に?
うーん……これはまた問題がありまして。山本は私が制作じゃない方がいいのかもとも思うんですよね。私と結婚していることがしがらみになって、彼をすり減らしているんじゃないかと。もちろん範宙遊泳の創作に私は貢献していると思うし、私の仕事が劇団にも栄養になっているとは思えるんですけど、作家・演出家対制作者の関係性を考えた時にはめちゃめちゃつらくて、これをあと何年も何年も死ぬまで果たしてやっていくのかって。結婚しちゃったけど、結婚したら何か変わると思ったけど、変わらなかったし、未だに探ってますね、どういう関係性がいちばんいいのかを。それはロロと範宙の二足のわらじだからってことじゃなくて、私があの人と結婚してるからっていうのが障害になってると思う。
──距離をとるのが難しいということ?
私は結構ちゃんと距離とってると思うんですけど。でも向こうは私がどういう選択をしてもとにかく存在がイヤみたいで、そのたびに相当な喧嘩をして、その繰り返しですね(笑)。だから範宙1本っていう選択肢はあんまりないかな……。
あと私たぶん、自分で思ってるよりも演劇が好きだから……。いつか子供を産んで演劇から離れるかなっていう気も前はしてたんだけど、真剣に考えたらすごいそれはイヤだなって思って。だから今はどうやったら演劇を続けられるか考えてます。
▼両劇団の今後のヴィジョン
──両劇団ともどういう感じになっていくんですかね。3年後、5年後……
……そういうことを考えるのが本当は制作さんの仕事だと思うんですけど、正直今、わかんなくなっちゃってて……。私はある種、作家に依存してるタイプだと思うんですよ。だから究極言うと、作家が「もう書けません、やめます」って言ったら終わっちゃう。だから実は制作者に向いてないかもしれないなと思うことはありますね。もう少しそこを組み立てられたら劇団もステップアップしていけるかもしれないんだけど……。
──向いてないとは思いませんけどね。「背伸び」させるのはフェスティバルや劇場のプログラムディレクターの仕事だったりもするし。でも劇団のことをずっと考えられるのはやっぱりその劇団の制作者だから、作家の側に寄り添う形でいるのも、それはそれでアリなんじゃないですか。
……大学卒業のタイミング(2011年3月)で、実は商業演劇の仕事をするかロロを続けるかで迷ったんですね。その時に、先生だった舞台監督さんに忠告していただいたんですよ。「仲間たちとの劇団にある時期を捧げるっていうのはすごく尊いことだけど、作家が書けませんって言って放り出された時に、スタッフとしてのキャリアとかもっと先に行けたはずのものが、留まることになってしまうよ。本当にそれでいいの?」って。実際、制作会社とか芸能事務所のマネージャーとか、いくつかお話もらったりしたんですけど、でもそれよりもロロをやりたい、そっちに賭けてみようって思ったんです。
──特にここ10年くらいでいわゆる「演劇すごろく」が崩壊して、どうステップアップしていくかという成功モデルはずいぶん変わりましたよね。そこに関してはどういうヴィジョンを持ってますか?
うーん……ロロに関しては、作家の創作ペースとか表現したいことを考えると、果たして広い劇場で大規模にやり続けるのがいいことなのか、ちょっと断言できないですね。旗揚げ2年目からノルマ制度をやめて、俳優に少なくても絶対ギャラを払うって選択をしてきたけど、劇場費が100万200万かかるような劇場でやりたい表現も全部やっていくのは、手打ち公演ではきつい部分もあって、今後どうしていくのがいちばんいいのかは悩んでます。
──そういう意味では、高校演劇のフォーマットにのっとった連作の「いつ高」シリーズ(「いつだって可笑しいほど誰もが誰か愛し愛されて第三高等学校」シリーズの略称。2015年11月〜)は、高校生たちに伝えたいことがあるんだ、っていうメッセージ性と創作への初期衝動をすごく感じます。抜け感があるのでは?
「いつ高」は久しぶりに三浦くん自身がやりたいって言い出した企画なんです。実は2014年くらいからは、演劇を続けるのがしんどそうにも見えたから、別に1年くらいやらなくてもいいじゃん、書きたいものが書きあがったら劇場とるって選択肢もあるよ、って話したこともあったんですよ。三浦くんは、メンバーのためにもコンスタントにやり続けなきゃってなってて、ちょっと疲れてきちゃったんじゃないかと思っていたので、その時期に比べると、「いつ高」はやりたいことが見つかった!って漲ってる感じがすごくあります。
やっぱり、三浦くんの書く言葉が本当に素敵だなって思うから、やり続けていくしかないですよね。

ロロ いつ高シリーズ(いつだって可笑しいほど誰もが誰か愛し愛されて第三高等学校シリーズ)vol.1 『いつだって窓際であたしたち』 撮影|三上ナツコ
──範宙遊泳のほうはどういうヴィジョンを? 海外にも招聘されるようになって、一気に視野がひろがってる感じがビシビシしますけど。
範宙は、自分たちの表現が、能や歌舞伎のように伝統芸能として未来に残っていくだろう、くらいの気概でやっていくというか。書くことはやめないでしょうね、山本は。「自分は現象を書くんじゃなくて人間を書くから、人間がいなくならないかぎりいくらでも文章は書ける」って言ってました。決してエンタメではないし、最近ますますアート寄りになってるとも言われますけど、でも分かりやすいことは誰か他の人がやってるから、別に範宙でやる必要ないよねって思ってます。
でも劇団員が売れること……これについてどうしていくかは作家性とはまた別の問題というか。海外公演ばっかりやっていくことが果たして俳優にとっていいことなのか?っていうのはあります。今の日本の演劇界のモデルケースにはそれはあまりハマらないし、そもそも海外で演じても観られなくて評価を受ける機会がないから、経験値としては培われるけど日本では仕事が来ない、ということになりかねない。そういう現状とどう向き合っていくかは、劇団の問題としてあります。
──そこはチェルフィッチュ以降の、海外に出るようになった俳優たちにとって、かなり大きな問題だと思います。このシリーズで前回インタビューした武田力くんのように俳優がアーティストに転身するような例もありますけどね。
結局、俳優自身がどうしたいかだと思うんです。「売れる」って言ってもいろいろあるから。劇団のスタンスとしては各々好きなことすればいいし、海外公演には出ないっていう選択肢もアリだと思う。
ほんとに集団って厄介だなって思いますね。主宰や制作者が劇団を導いていくのが正しいのか? でも俳優もみんな等しく劇団員ではあるし、別に私たち(主宰と制作)だけが経済的に得してるわけでもないから、引っ張っていくのもたぶん限界があります。そう思うと私自身、たぶん究極的には劇団じゃなくて、作家っていう存在と向き合っているのかもしれない。それじゃいかんいかんと思ったりもしながら。
▼範宙遊泳が「アジアに売れる」理由
──今、海外の話が出ましたけど、範宙遊泳で海外に行ったのは2014年5月のマレーシアが最初ですよね。
はい、TPAM2014の時に、マレーシアのカキセニというアート支援団体の(ロウ・ナイ・)ユエンさんに即決で呼んでもらって。私は海外に行くこと自体、それが初めてでした。

2014年、マレーシア。共同制作した『幼女X(Gadis X)』開演直前。席が足りず床に座る観客たち。
──その時の感じって覚えてますか? 初めての海外ってインパクト強いじゃないですか。
後でいろんな人たちから「恵まれてたね」って言われたんですけど、カキセニがそれなりに潤沢な資金を持っている団体だったので、警備員がいてプールのある高級コンドミニアムに泊まって、治安が心配だということで移動はぜんぶタクシーで、本当に快適でしたね、今思うと(笑)。
結局マレーシアには26日間滞在して。それからタイに行ったのが2014年の秋。インドにはまず2015年にリサーチで行って、翌年に公演して。それから今回2016年4月のシンガポール滞在ですね。
──マレーシア、タイ、インド、シンガポールと、範宙遊泳が開拓しているルートはかなり独自路線ですよね。
そうですね……範宙が「アジアに売れる」理由は理解できたような気がします。TPAMでも野村政之さんが売るつもりでディレクションしてくれて、2人の俳優とプロジェクターだけでコンパクトに上演できるし、テキストもシンプルだから『幼女X』がいいって言ってくれて。
で、実際の反応としては、特に欧米の人には「なんでわざわざあの(プロジェクターを使った)手法をやってるの?」って訊かれたんです。英語ができないので、細かいニュアンスが正解かはわからないですけど、私はそれを「なんであんなアナログな(ロークオリティな)映像の使い方をするのか?」っていう意味だと受け取りました。
でもアジアの人たちは「自分たちでもこれはできる!」って思ったみたいで、「貧しい資源の中でもパソコンとプロジェクター1台でこんなことができるということを、自分たちの国でも見せたい」と最初のマレーシアの時にユエンさんに言われたんですね。「範宙遊泳のようなやり方はマレーシアにはない。演劇といえばこうっていう固定したスタイルしかないから、こんなこともできるってことを提示してほしい」と。日本も今はそっち寄りな気がします。限られた資源の中から何ができるかっていう。それはアジアが今持ってる共通の方向性だと思うんですね。
▼シンガポールのこと、そしてインドの衝撃

2016年、シンガポール。共同制作するThe Necessary stageや俳優たちと。
──直近のシンガポールは、あちらの劇団とのコラボレーションで行ったんですよね?
そうです。TPAM2015でタイのDemocrazy Theatreとコラボレーションした時に、臨時の通訳で入ってくださった鈴木なおさんという方がいて。彼女が「絶対合うと思うから」って言って、シンガポールの劇団The Necessary Stageを紹介してくれたんです。創立30周年で文化勲章も取っていたりして、財力もキャリアもある。範宙遊泳とはまた違うやり方ですけど、プロジェクターで映像を映すこともやってるようです。
それで彼らの持っているシンガポールの劇場に行って、来年の上演を目標にディスカッションとワークショップをしました。あとリサーチですね。いろんな場所に連れて行ってもらって、まずはテーマを決めるところから共有していこうと。彼ら的には事前のスカイプの打合せでテーマを決めたかったと思うんだけど、山本(卓卓)が「僕は現地に行って、どんな風が吹いてるか、どんな匂いがするか知ってからじゃないと、何をつくるかは決められない」と主張したんです。滞在中は毎日終わる時に必ずディスカッションしようっていうことも、こちらから提案しました。向こうは演出家と劇作家が別々なんですけど、俳優は3人ずつ、両国で6人いました。
──日本からの3人は?
熊川ふみ、田中美希恵、埜本幸良。あとアートディレクターのたかくらかずきも。向こうが「絵文字」に興味をもっていそうだったので、たかくらにも入ってもらいました。
──シンガポールの俳優は何歳くらい?
聞かなかったけど、たぶん同じくらいか歳下なんじゃないかな? 大学を出たばかりって言ってたけど2年間兵役があるから、25、6とか? 脚本家と演出家は50オーバーです。演出家が山本と干支で2周り違うから「おお、我が息子よ」って言ってました(笑)。今までのコラボレーションに比べると年齢差がありますね。
──町のリサーチではどんなところを?
リッチな町と貧しい町、どっちも見たいってお願いしたんです。異国で人の住んでる家を見るってなかなか面白いということにインドで気づいて、家も見せてもらいました。
例えばリッチな町では、メイドさんは人種によって賃金が決まっていて、確かフィリピン人がいちばん高いって言ってたかな。一方でもうちょっとローカルなエリアを見た時に、全然キレイな団地で。でもそれは、そういう団地を与えることで貧しさを外に見せないようにシンガポール政府がコントロールしてるそうなんです。外壁を5年に1度塗り替えることも決まってて、とにかく汚いところは見せない。物乞いの人もいなかった。私があんまりその話をするもんだから、劇作家の人が「何でももは物乞いの話ばっかりするの?」って。なんせインドの物乞いは凄かったので……。車が止まればみんな寄ってきて窓を叩くし。
──インドは凄かったですか。
凄かったですね。インドの初日、泣いてしまって。3歳くらいのやっと歩いてるくらいの女の子が寄って来たんですけど、服もボロボロで(栄養失調で)お腹膨れてて、これはお金をあげるべきなのかと迷って。でも現地の人もあげなかったので、あげないのがルールなのかと思ってそれに従ったけど……。
ホテルに行ってから山本と「あなたならどうする?」って話したんですけど、山本はその時に「日本のホームレスにしないことはしない、って俺は決めた」って言ってました。彼の方がひとりでタイに行ったりして、より多くの貧しい人を見てるからかもしれない。タイなんかは純粋な物乞いじゃなくて、ヤクザの元締めからのビジネスみたいなこともあるから、彼らにあげても彼らが潤うわけではないし、そうそうあげてもいられないし、って。でも「その時思ったようにすればいいと思うよ」って言われました、私もタイに行った時は、駅にいた赤ちゃんを抱いたお母さんに小銭を全部あげて帰ってきました。

2016年、インド。『われらの血がしょうたい』でケララ国際演劇祭に参加。公演終了後、現地の皆さんと。
▼演劇が手段として求められる時代?
──海外を経験して、集団についての意識が変わったというのはありますか?
それはありますね……。たぶん「何のために演劇をするのか?」みたいな問題意識を持たないと続けられないと思うんですよ。作家はもちろん作品にそれを込めているだろうけど、等しく俳優もスタッフも持たないとダメなんじゃないかなって。海外の人の方がそれをちゃんと持ってる気がしますね。
そういう演劇への意識を、私は海外で初めて知ったんです。演劇が何かの手段であるということを。でも例えば──これはロロの話になりますけど──ロロってそうじゃなくて、何かの手段として演劇をやってない。そこがロロのいいところだと思うんです。その良さをなるべく殺さないようにしたいけど、それだとよりいろいろな選択がしづらいですね。何かの手段として演劇を考えた方が、意外と簡単だったりするから。
──わかります。そのほうがいろんなところと繋がりやすいよね。
例えば助成金をとる言葉も表現しやすかったり、作家の言葉も強い意志があるように聞こえるから。三浦くんは意志がないわけじゃない。たぶん彼は、何かの手段じゃなくてもっと純粋なものとして演劇を捉えてるから。でもそれは果たしてこれからの社会で求められることなんだろうか、っていうのは引っかかってきてますね。
──僕もそこにはジレンマがありますね。少なくとも今後数年は、演劇がその効力や機能を求められるという傾向は日本でも続くだろうし、作家なり制作者なりがそれを他者に説明できる方が圧倒的に強いだろうと思う。でもそれでいいのだろうか?って葛藤も常にあって、どっかで「演劇は役に立つ」というのは方便にすぎないなって気もしちゃうのね。別になんかのためにやってないし、って部分は絶対あるし、やっぱり創作意欲の純粋性っていうのも大事だと思うんですよ。芸術への初期衝動というか。そして三浦くんはその最たる純粋意欲のカタマリだっていう感じがするんです。
その「求められる」感が顕著になったのは、震災以降なんですかね? F/T11公募プログラムにロロが出たじゃないですか(『常夏』)。三浦くんは宮城県の出身なので、幼少期過ごした女川が流されちゃって、親戚一同ご無事ではあったけど、家族は被災してるじゃないですか。で、アフタートークで「このテーマのF/Tで、ボーイミーツガールやるんですか?」って質問されたんですよ。その年のF/Tは「私たちは何を語ることができるのか」というコピーがついていて、今、震災後の今、っていうニュアンスが含まれた否定的な質問に私は感じました。三浦くんはその時なんて答えてたかな……確か「それしかできませんから」って言った気がする。絶対言いたくなかったんですよね。自分が宮城出身だって言えばそれだけで「加点」されるから。「被災してる場所の人なんだ」って、そういう見方になるから、あの時は極端に仙台や女川の話を避けてましたね、三浦くん。でもアフタートークでそういう質問されちゃうんですよね。じゃあ政治劇やればいいんですか?……ってことでは当然ないわけで。
でも、日本人ってボカすことができるじゃないですか。海外の人たちは、国や社会に対しての問題意識を作品にストレートに入れてやるけど、物語としてメッセージをボカしながら込めることができるのは日本人の特性なのかなって思うんです。だからその両方のバランスを取っていくことができるかもしれないなっていうのは、海外に行って思いました。まったくのフィクションでもなく、アクティビストのつくる演劇でもなく。

ロロ『常夏』 撮影|三上ナツコ
──そこは本当にそう思う。ただ日本の作家はそれが今のところどちらかというと内弁慶的なドメスティックなものになってしまっていて、いっぽう海外に出るためにはただわかりやすく政治的になっていくしかないのだとしたら(もちろんそんなことはないはずだけど)ちょっと残念だよね。
ほんとにその、求められることに応えた方が売れそうな感じっていうのはね……。でもちょっと話は変わりますけど、演劇といってもいろいろあって、芸能人が出てる芝居だとまた違うものが求められるじゃないですか。究極言うと、やっぱりTPAMの海外演目とかを観た後に、もうエンタメ演劇観たいって思わなくなっちゃったんですよね。それを観て果たして今の自分が面白いと感じられるとは到底思えなくなっちゃって。海外かぶれとは思われたくないですけど、どうしたってTPAMとかで観る作品には切実さがあるので。もちろんみんな切実にものをつくってるとは思うけど、1年に何本も何本もルーティンのようにプログラムされているエンタメ演劇を、前と同じようには面白がれないだろうなって気づいてしまったのが、海外に行って自分がいちばん変わったことです。
言語の問題も大きくて、日本人が日本語で喋る演劇は日本人と日本語がわかる人にしか向いてないですよね。でも最初から例えば英語でつくられた演劇は、そもそもの発言の先がめちゃくちゃ複数じゃないですか。その違いって相当大きいなって思うんです。
でもまったくこんなことになるって、演劇始めた頃は思ってなかったんですよね。海外の人と演劇するとか。
──想像してなかった?
まったく。それは自分たちが変わったんじゃなくて、国が変わったんだと思います。きっとオリンピックによるところは大きくて、そういう未来に今立ってると思うんです。オリンピック終わってどうなっちゃうかはわからないけど、それにともなって、つくる演劇も変わっていくんだろうなって。そんなこともないのかな。どうなのかな? ……オリンピックって何なんでしょうね。今はラッキーな海外バブルだとは思ってます。

2014年、タイ。『幼女X』でバンコクシアターフェスティバルに参加。終演後、舞台上からの景色。
──今、いろんなアーティストが海外に出始めていますよね。いったん出れば海外の友だちも増えてネットワークもできるし、知識も経験も増える。それはオリンピックまでのバブルかもしれないけど、やっぱりどこかで自分から「外」を志向して運をつかみに行った人たちがそうなってるとは思うんですよ。でもそうじゃない人たちも当然いるじゃないですか。海外に関心を持てない、もしくは持つのが怖い、だけどいつか声がかかるのは待っているという人たちがたくさんいて、でも別に自分は日本で満足だしっていう自己処理もきっとそれなりにできてしまう。そこの温度差がひらいていった時に、さて2020年の後にどうなるかというのは思いますね。
……更新していくものなんだなって思います。これは時代のせいなのか、自分が歳を重ねたからなのかわからないけど、こんなにも毎日が変化していくんだなって思う。演劇にかぎらず、震災があったことも、テロがあったことも含めて……。
それを明確に意識したのが『アメリカン・スナイパー』(2014年)を観た時で、携帯電話が出てくる戦争映画がもうつくられるんだって衝撃だったんですね。私にとって戦争はそれまで本とか映画とかテレビの中にあるもので、そういうもので触れたり、祖母から話を聞いたりもしたけど、そこに携帯電話は出てこなかった。でも『アメリカン・スナイパー』は戦地で妻とケータイで喋りながら銃を撃つじゃないですか。昔のことじゃなく、今も戦争があるんだっていう、そのことにすごく傷ついて、自分が生きてるってことと外側のことを関係づけて考えるようになったんです。
今までは単純に義務教育受けて、大学で学びたい演劇学んで、順等に成長してやりたいことやってふつうに生きてきたけど、その先になって選択肢がうわーっとひろがってしまったというか。今は自分の選択1個でいろんなことが決まっていってしまう。その中に、演劇で何をするかっていうこともあるし、演劇をやらないという選択もあるし、まあそうやって決めていくことが大人になるってことだと思うんですけど、そういう時期に私自身はロロと範宙遊泳でいろんなことがあったし、海外も行ったし、結婚したのもそうだし……そこにさらにオリンピックが来ちゃうんだなっていうことを今感じてますね。前は単純に、その瞬間の自分のことと、ちょっと周りの人のことだけを考えて、楽しく生きていけたはずだったのに。
▼移住すること、子供を産むということ
──最後の質問ですけど、今後、日本に住まないっていう選択肢もありえますよね。例えば子どもを育てるっていうことも含めて、今の日本が生きるうえでベストな環境とは僕には思えないんです。フィリピンとか、確かに貧しい人はたくさんいるけど、子どもたちはそれでも幸せそうだったりするし、こういうところなら人間を育てるのも楽しいかもしれないと思ってしまう。あるいはいろんな都市で、日本に住まないという選択をした人たちに会ってきて、以前よりも海外で暮らすという可能性がかなりリアリティを帯びてきた。そのことはどう思ってますか?
私はあんまり日本で子育てするのがキツイかもとは思わなくて……っていうのは私が東京生まれ・東京育ちだからだと思うんですけど。演劇の人でも、東京を出ていった人が結構いるじゃないですか。でも私は東京に対してそんなに不満がないんですよね。新宿区生まれで都会育ちで、特にオススメできるいいところもないですが、東京の存在自体を問うたことがなくて。私の認識だと場所より人なんですよね。家族がいる場所の方がいいとか、友だちのいる場所がいいとか、そうやって人が先に来ちゃうから、あんまりこの土地がどう、みたいに考えたことは正直ないかもしれないです。
だけど子どもを産むっていうことに対しては最近すごく考えます。単純に、怖い。怖いということがあまり語られないのはなぜなのか? 保育園の問題とか、支援が少ないから出生率が下がってるとか問題になるけど、そういう云々ではなく、子どもを産むということ自体が恐怖である。めちゃくちゃ子ども欲しいし、そろそろ産むつもりではいるんですけど、めっちゃ怖くない?って。
──怖いというのは?
自分が命を生み出すことがです。あんまりその先のことは心配していなくて、うちは東京に実家があるし両親元気だし、そんなに裕福じゃないけど、自分が育ったくらいだからまあどんな環境でも大丈夫、って楽観的に思えるんです。でも産むこと自体は怖くて。今の環境をがらりと変えて、お腹に子どもを宿したまま何か月も生きて、産み落とす。未知なことすぎてすごく怖いんですよ。……って話を母親にしたら「ほんとにビビりだよね」って言われたけど(笑)、私にとってはビビってる感情の方が先に来るから、日本で産むとか海外で産むとかはあんまり関係ないですね。
でも、移住という選択はなくはないと思います。住めるな、というか、住みたくないとは思いませんでした。シンガポールは「だったら日本でいいかな」って感じでしたけど(笑) ホテルも良かったし、いいところしか見てないからかもしれないけど、マレーシアとタイは全然平気。インドは水に気を遣うのがすごく疲れました。歯磨きもミネラルウォーターでしないといけないのはしんどい。でも現地の人はゴクゴク飲んでるし、慣れれば大丈夫なのかもしれないし、住むのが絶対無理っていうわけではありませんでしたね。
* * *
坂本ももと知り合ってから6年が経ち、そのあいだにいろんなことが変わった。世界も、わたしも、彼女とその周辺も……。実は最初に出会った頃の彼女の印象は「お母さん」だった。若いロロの子たちをまとめているという印象が強かったのかもしれない。けれど今は、むしろひとりの人間、いやこう言ってよければひとりの女の子に思える。それはもちろん幼くなったということでは(当然)なくて、この世界に対してひとりで(も)対峙する存在になった、と感じるからだろう。
未来は結局いつだって若い人たちがつくっていくのだと思う。